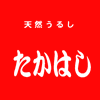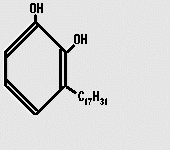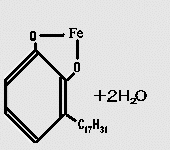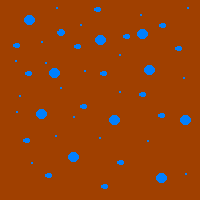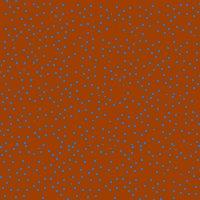少し専門的に科学してみる
| あまりお目に掛かりたくない「亀の甲」や図表が出てきますが、しばらくお付き合いください。バックの亀の甲はウルシオールです |
天然うるしとは
漆は漆の木の樹液です。漆科の植物は東南アジア全域に分布し果物のマンゴーもその仲間です。漆科の種類は600種類ほどと言われますが、樹液を採取できるのは、漆科の中でも漆属に限られます。漆属の中でも大きく分けて三種類が塗料として利用さており、国内で利用される漆はウルシオールを主成分としたものです。
漆掻きは平均的に4〜5日置きに行われます。これは木を痛めずに樹液を作るために必要な時間です。屋外の仕事ですから雨が降ることも在ります。掻いた傷口に雨が当たるのは良くない様で、雨天の場合は行いません。 |
産出国による樹液(主成分)の化学構造の違い |
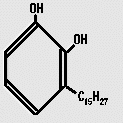 ウルシオール |
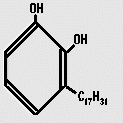 ラッコール |
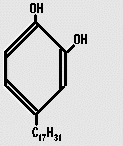 チチオール |
日本・中国・韓国で産出 |
台湾・ベトナムで産出 |
タイ・ビルマで産出 |
詳しい方は油の構造と似ていることが解ると思います
| 漆の成分 この成分はあくまで一般論で、採取する時期により特性も変化し名称が変わるくらいですから当然成分構成は同一の木から採取しても一定ではありません。生き物ですから当然とは云え厄介なことです。こんな所も工業化され難い点かもしれません。 |
一般的な生漆の成分(モデル)
|
うるしの名称
漆樹液は、採取時期により名称(品質も)が異なります。市販されている漆液は精製されていますが、当然精製過程でブレンドされたもので用途に応じた混合を行っているため、非常に重要なプロセスでもあるのです。原料となる樹液の名称を解説します。 漆の樹液の採取は6〜11月(地域で多少前後する)に行われますが、おおよそ新緑から紅葉そして葉が落ちる範囲になります。採取した樹液そのものは「荒味漆(あらみうるし)」と呼ばれます。 |
| 荒味漆(掻いた時期による)の名称 | ||
| 6月中旬〜7月中旬 | 初辺(初漆) | 小さな掻き口を付け、採取量も少ない |
| 7月中旬〜8月下旬 | 盛辺(盛漆) | 最も品質の高い漆とされます |
| 8月下旬〜9月下旬 | 遅辺(遅漆) | |
| 裏目漆 | この頃には樹皮が硬くなり、皮を削り採取します | |
| 止漆 | この止掻きで、樹液の分泌は止まります | |
| 枝漆 | 切り倒した後、太枝から掻き採ったもの | |
| 〜11月下旬 | 瀬〆漆 | 細枝に切れ目を入れ掬い取ったもの |
採取時期による名称は一般的と思われるものを用いていますが、地域によっては通じないかもしれません
|
漆の乾燥(固化)は一般的な絵の具や塗料のような溶剤の揮発によるものではありません。主成分であるウルシオールが酸化することで高分子を形成します。常温乾燥を行う場合はラッカーゼと云う酵素の働きで固化します。又、高温(熱)によっても重合反応が起こり固化(乾燥)します。 酵素による固化メカニズム 高温による固化 |
漆の乾燥時間
| 乾燥時間は単純に計算することが出来ません。常温(生活環境の温度、15〜30℃)完全に乾燥した状態(酵素の活性が失われる)を定義しても肉眼では見分けることが困難です。まず、樹液によって乾き具合がかなりばらついています。湿度・温度によっても酵素の働きが変化しますから、これも要因の一つとなります。そして空気と触れている表面(酸素の供給がされ易い)から乾いていきますから塗膜の内部は遅くなります。常温乾燥で作業に支障が出ない程度に乾燥するまでの時間は、漆の状態により半日(かなり早い)から二日、温度は夏場の気温(20〜30℃)ならば湿度も高いので早く、冬の寒い時期は温度と湿度の低さで遅くなり乾燥時間を要します。零度付近から零下になると殆ど乾燥しなくなります。最終的な製品になった漆器は出来あがった時点では完全に乾ききっていません。内部までウルシオールの活性が失われるまでは「臭い」や「かぶれ」の心配があります。その期間は1〜6ヶ月(置かれている環境による。特に温度と湿度)と考えられ、光沢を上げるために油が混合された場合など更に時間が必要と思われます。油(JIS規格にあるくらい一般的なこと)の量が多いと半年でも乾燥しない場合もあるようです。
|
漆は丈夫なのか?
色と顔料について
精製漆の種類
精製による成分の構成変化(モデル例)
精製漆の種類 (日本工業規格(JIS)による)
|