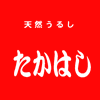|
|
実際の制作工程となっておりますが、全ての漆器がこのような工程で制作されるわけではありません 教科書的な意味合いの本格的な仕上げです 例えば、お椀の場合ですと一客数万円で売られているとお考えください |
| 本堅地(ほんかたじ)黒呂色(ろいろ)仕上げの工程です 本堅地は加工方法で一番工程数が多いため、その他の方法ではその一部を省いた制作工程となります 本堅地の工程が理解できれば、基本的な工程の流れは変わることはありません 制作の流れを理解していただく目的ですので、同一の作業が繰り返し行われる工程は一回に省略してあります 実際に制作する場合は、もちろん同一作業であっても行います |
| 実際の作業工程を行った実写の画像です 画像は会津で実際に撮影用に制作したものです 画面上では工程による表面の違いは見分けにくいと思います それぞれの拡大画面がご用意してあります |
木地固め(きじがため) |
|
布着せ(ぬのきせ)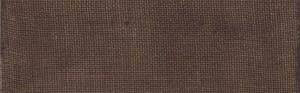 |
補強を行いたい部分に、麻布を糊漆(のりうるし)で貼り付けます |
布着せ研ぎ(ぬのきせとぎ)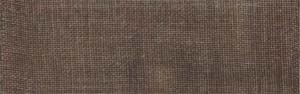 |
粗目のサンドペーパーで布着せ面を平らに削り揃えます |
布目摺り(ぬのめずり)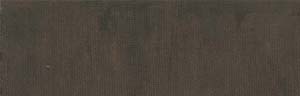 |
布目の中の溝に、切り粉錆(きりこさび)を箆(へら)で擦りつけ凹凸を無くします |
地付け(じづけ)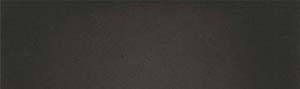 |
糊漆(のりうるし)に地の粉を加え練った糊地の粉を箆(へら)で下地付けを行います |
地付け研ぎ(じづけとぎ)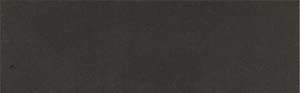 |
十分に乾燥した糊地の粉の表面を粗目の砥石で研ぎ出します |
地付け固め(じづけがため) |
樟脳(しょうのう)油を加えてシャブシャブな状態の生漆を染み込ませ、砥いだ面を固めます |
切り粉付け(きりこづけ)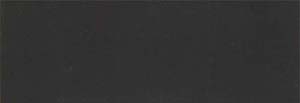 |
地の粉、砥粉(とのこ)、生漆(きうるし)を混ぜ合わせた切り粉錆(きりこさび)を用いて下地付けを行います |
切り粉付け研ぎ(きりこづけとぎ)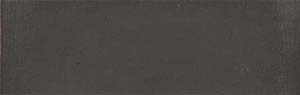 |
乾燥した切り粉錆を粗目の砥石を使って研ぎ出します |
切り粉固め(きりこがため) |
樟脳(しょうのう)油を加えてシャブシャブな状態の生漆を染み込ませ、砥いだ面を固めます |
錆び付け(さびづけ)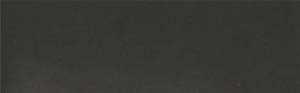 |
砥粉(とのこ)と生漆(きうるし)を混ぜた錆漆(さびうるし)を用いて下地付けを行います |
錆付け研ぎ(さびづけとぎ)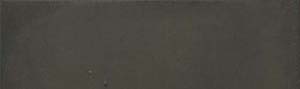 |
乾燥した錆漆の表面を粗目の砥石を使って研ぎ出します |
錆固め(さびがため)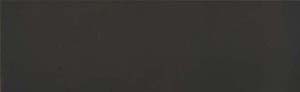 |
樟脳(しょうのう)油を加えてシャブシャブな状態の生漆を染み込ませ、砥いだ面を固めます |
| ここから塗りの工程です |
下塗り(したぬり)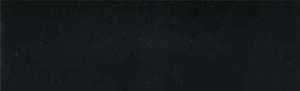 |
刷毛を用いて黒中漆(黒で仕上げる場合、彩漆の場合は透中漆)を平均的に塗っていきます |
下塗り研ぎ(したぬりとぎ) |
乾燥した塗面を600番程度の砥石で研ぎ出します |
化粧錆付け(kしょうさびづけ)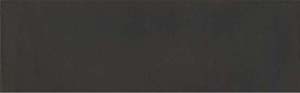 |
表面がきれいな平面にならず凹になっているので、錆漆を付けます |
化粧錆研ぎ(けしょうさびとぎ)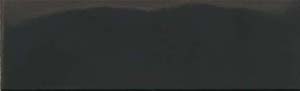 |
乾燥した錆漆面を600番程度の砥石で研ぎ出します |
下塗り(二回目)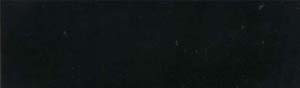 |
刷毛を用いて、黒中漆を平均的に塗り付けていきます |
下塗り研ぎ(二回目)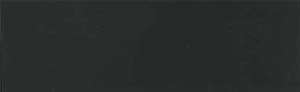 |
乾燥した塗面を600番程度の砥石で研ぎ出します |
中塗り(なかぬり)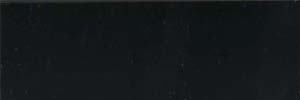 |
刷毛を用いて、黒中漆を平均的に塗り付けていきます |
中塗り研ぎ(なかぬりとぎ)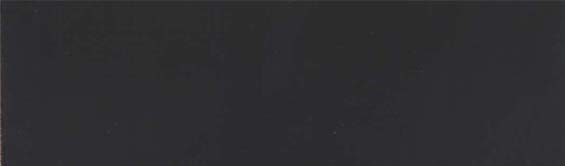 |
砥石を800番程度に上げ(キメの細かいものに替え)、塗面を研ぎ出します |
上塗り(うわぬり) |
黒中漆から黒呂色漆(くろろいろうるし)に替え、平均的に刷毛を用いて塗り付けていきます |
上塗り研ぎ(うわぬりとぎ) |
砥石を1000〜3000番程度に上げ(キメの細かいものに替え)、塗面を研ぎ出します |
摺り漆(すりうるし)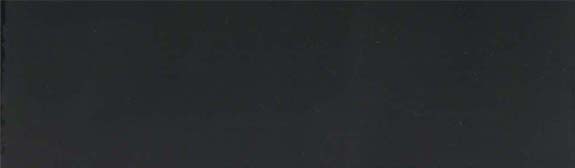 |
研ぎ出した面に摺り漆を行います |
胴摺り(どうずり) |
水で溶いた砥粉(とのこ)を綿につけ、胴摺りを行います |
摺り漆(すりうるし)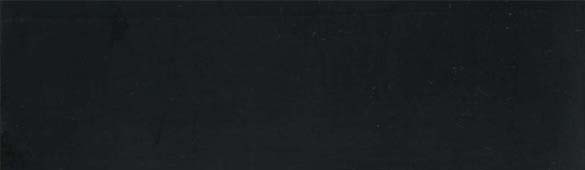 |
樟脳(しょうのう)油で溶いた生漆を用います |
磨き(みがき)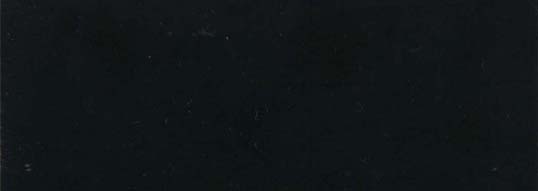 |
菜種油で溶いた呂色上げ粉を、指先に附けて磨き上げを行います |
| 以上で塗りの工程は終了です |